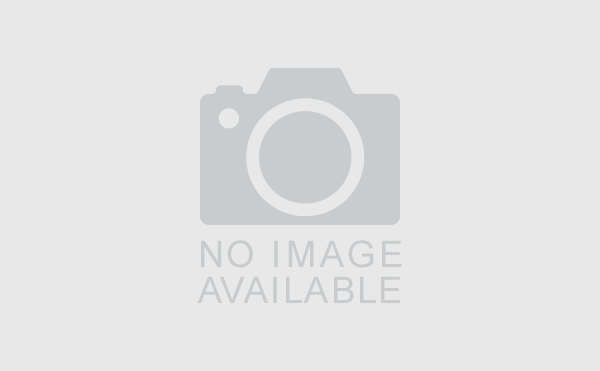ある日、キラキラネームを考える
命名の際、キラキラネームが使用されるようになったのは90年代からだという。私が教育実習で学校現場にいたのは90年代後半だったが、読めない名前の生徒はほとんどいなかった。つい10年ほど前くらいからの話だと思っていたため、実習していた頃からすでに存在していたとは知らなかった。
今から17年前、フランスでのインターン期間中も、その存在を意識してはいなかった。
インターン初回の講義は、書道(習字)にした。文字に興味を持つ生徒がそれなりにいるのではないかと想定し、参加者が見込めると思ったからだ(最初から人数が少なかったら凹むし)。日本で硯・太筆・細筆・固形墨・墨汁・下敷・文鎮を30セット、半紙100枚・半切50枚を揃え、まあ足りないことはないだろうと考えていた。だが嬉しい誤算というか、日本クラス開講初日ということで、受講希望者だけでなく取り敢えず様子を見に来た見物人も含め、30人以上の生徒が参加してくれた。そのため、用意したセットは交代で使ってもらうことにした。フランスの高校生は大人びて見えるとはいえ、筆を持った途端に隣の子と遊び始めたり、席に座れない生徒がガヤガヤしていたから、こちらの話に集中してもらう必要がある。そこで私は、各自の名前に合わせたい漢字を調べ、書いてもらうことで、参加者全員に興味を持ってもらおうと考えた。
一人一人の名前を聞き、日本から持参した漢和辞典で発音に似た漢字を調べる。
「これらが該当するけど、どれがいい?」
いくつかの候補を提示すると、生徒は「この字がかっこいい」などとまず形から入る。
「その漢字はこういう意味を持っているんだよ」
私が字の語源や内容を説明すると、全員が形ではなく意味で漢字を選んだ。フランス人はペットなどの名前を音の響きで付けたりすると聞いていたので、字の含みはさほど重視しないのかと思っていたのだが、やはり自分の名前となると意味のあるものにしたいらしい。
字が決まった生徒からコピー用紙で練習してもらう。同じ名前でも選ぶ漢字はそれぞれなので、「それ、どういう意味があるの?」などとお互いにやり取りしていて、クラスが活気づく。私は一人ずつ漢字を調べているので、目の届かない生徒が手持ち無沙汰にしていないか心配だった。幸い、皆が真剣な表情で練習していたので、退屈しているような参加者はほぼ見られなかった。筆と墨に慣れたところで半紙に清書してもらう。みんな初めての体験ということなので、字をなぞったりするところは大目に見る。思い切りのいい生徒はパパッと終わらせていたので、交代での使用も思っていたより混乱せずに済んだ。
「持ち帰っていいですか?家族にも見せたいので」
書きあがった半紙を左右にヒラヒラと振りながら、嬉しそうに男子生徒が問いかけてくる。早く乾かして、鞄に収まるよう丸めたりしたいのだろう。家に帰って漢字の意味を説明する際、親御さんから自分の名前の由来などを教えてもらったりするのだろうか。そんな家族団らんを思い描き、和やかな気持ちになる。
大半の生徒が清書した習字を持ち帰ってくれたので、初講義は成功したと思っておきたい。きちんとした講義は2回目以降で行ったが、生徒数は減る一方だったので、初回の受講者数はキラキラネーム作り様様といったところだ。
参加した生徒から授業の様子を聞いたのだろう、その後受講していなかった生徒や教員からも「私の名前を漢字にして!」と依頼を受けた。できれば書道にも興味を持って欲しかったが、クラスに誘ってもいい返事は返ってこなかった。受講生が日本クラスのことを広めてくれただけでも良しとしようと気を取り直し、私は良い意味を含む字を選んで依頼者の名前に当てはめていった。
メンターのマリーのように日本人名と似ていて選びやすい人もいれば、思うような漢字が見つからず迷ってしまう人もいる(ちなみにマリーは『真理』を気に入っていた)。あるとき教員部屋で、ヴァレリーという女性教師(アンヌ・マリーの姪ではない)から名前の字を考えてと頼まれた。
「一番いいものにしてね」
これまでも、私が漢字を選ぶときには良い意味を持つものにしてきたが、依頼相手から念押しされたのは初めてだ。彼女は栗毛で、ベット・ミドラーさんを縦にも横にも一回り大きくしたような女性。意見をはっきり言うタイプで声も大きいし、華やかな色合いの服やストールを身に着けていたから、迫力があるし目立っていた。私の選んだ漢字が気に入らなかったら躊躇せず態度に出しそうだ。
(『ヴァ』は『バ』でいいよねぇ……)
彼女の雰囲気からすると『薔』でもいいかと思ったが、「一番いいもの」となると、より喜ばしい意味があったほうが良さそうだ。バラは棘があるじゃない、とか言われても困るし。あれこれ考えてみて、私は『繁麗璃』という漢字を当てはめることにした。見栄えとしては画数が多くてごちゃごちゃしている。ヴァレリーも最初は、
「すごく複雑なのね!」
とあからさまに顔をしかめていた。
「どういう意味なの?」
私は漢字の下にフランス語で『繁栄をもたらす華麗なラピスラズリ』と書いて渡した。すると彼女の表情は一変。
「La prosperite!Splendide!!Lapis‐lazuli!!!」
と歌うように言葉を読み上げ、
「私って日本語でもマニフィック(素晴らしいとかゴージャスという意味)な名前なのね~!」
と教員たちの前で小躍りし、意気揚々とし始めた。
ヴァレリーの喜ぶ様を横で見ていたダニエルという女性教師が、
「私はどんな風になる?」
と食いついてきた。
「じゃあ、後で紙に書いて渡します」
「後で?今くれないの?」
私はゆっくり調べてから渡したかったのだが、ダニエルはこの場で書いてとせがんできた。間が悪いことに、私は漢和辞典を講義部屋に置いてきていて、教員部屋には持ってきていなかった。講義部屋の鍵はマリーが持っていたが、彼女は別の学校の授業があり退勤していたから、今日はもう入れない。
「私、明日・あさっては出勤しないのよ。早く教えて!」
ダニエルはソワソワしている。私は今ここで、漢和辞典なしに字を思い浮かべるしかなさそうだ。
(『ダ』の漢字は……)
駄・蛇・打・堕・唾。
って、よろしくない~!
私は他の字のイメージが浮かばないか、ダニエルの顔をまじまじと見つめた。彼女は小柄でぽっちゃりした体形。眼鏡をかけ、肩までの黒髪をちりちりのソバージュにしている。アメリカのTVドラマ『ビバリーヒルズ』シリーズに出演していた頃のガブリエル・カーテリス(アンドレア役)にちょっと似ている。
(この内容で大丈夫かしら?)
私は恐る恐る、漢字を書いた紙をダニエルに渡した。
「ヴァレリーよりすっきりしていい感じよね。それで、どんな意味があるのかしら?」
身を乗り出すダニエル。大きな目が更に見開かれている。
(期待しちゃってるよね……。言ってもいいものかな?)
「ブッダと出会った尼僧が徳を得る」
ポカンとした表情のダニエル。ものすご~く引いている。
徳は積むものだろ、ということはさておき、少しでも良い意味を付け加えてあげたかった一心で、私は彼女の漢字を『陀尼得』にしたのだが、案の定、彼女は分かりやすく落胆していた。
「今は辞書がないから。ちゃんと調べたらもっと素敵な意味の字が……」
彼女の反応に焦って取り繕う私が言い終わる前に、ダニエルは
「ありがとう。もういいわ」
と顔を背け、教員部屋から出て行ってしまった。
ゴメン。本当にごめんね。ヴァレリーと同じような、マニフィックな意味を期待してたんだよね?あなたの顔を見たとき、信心深そうな人だと思ったの。だけど、きっとあなたはクリスチャンだよね?それに、尼さんに例えられたら困惑するよね?(たとえ仏教徒でも信心深い人でも喜ばない気がする……)
以前にも、親交のある外国人の名前をキラキラネームにしたことはある。その際はお遊び程度にやっていたが、インターンのときは意味を考えてそこそこ頭を悩ませた。国際化が進み、海外で通用するよう、日本の家庭でもお子さんに欧米風の名前を付け、漢字を当てはめるケースが増えてきていると聞く。更に、最近のキラキラネームは、意味はさほどなくとも音の響きや字の見た目に重きが置かれることもあるそうだ。外国人の名前を漢字に当てはめることは、音に合わせて選ぶことに他ならなかったので、ついダニエルのことを思い出してしまった。もっと喜ばれる字を選んであげられたら良かったけど、浅識な私が自分の頭からひねり出せたのはあの程度だった。音から入って意味のある字を選ぶとき、あまりいい内容ではなかったりしっくりこなかったりすることもあるから、響きや見た目で決めるということも分からなくはない。
子どもの命名は親からの最初の贈り物とも言えるから、「一番いいもの」にしてあげたい・して欲しいという願いは誰しもが持ち得ているだろう。いいものの基準は人それぞれだから、意味に拘る人もいれば、形の美しさに価値を見出す人もいる。新生児には希望を聞けないから、ベストを決めるのは親の価値感になってくる。子どもが親と同じ感覚であってもなくても、いい名前だと思ってもらえたら親の最初の贈り物は成功だ。でも『繁麗璃』とかだと、テストのとき名前を書くだけでタイムロスしちゃうから、そういうときは簡単な漢字のほうが良かったのにと思われてしまうかも知れないな。ほんの少し教育現場にいた者が感じることとしては、読めない名前だらけだと、なかなか個人個人を覚えられなくてもどかしかったりするんじゃないかな(ふり仮名つきのキラキラ漢字ネームをカナだけで見せられたとき、一瞬誰だか分からないことがあるというのは私だけでしょうか)?