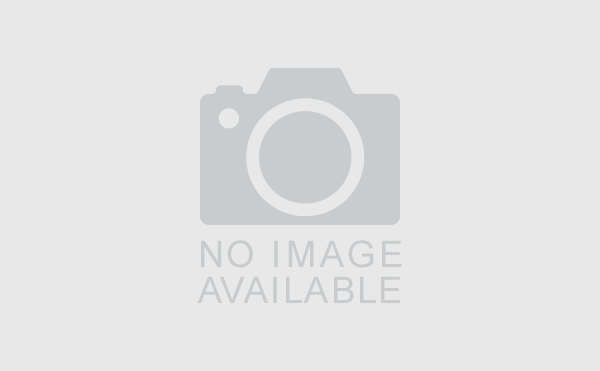ある日、禁じられた遊び
フランス私立高校でのインターン開始当初、私は生徒たちと早く仲良くなりたくて、将棋崩しや坊主めくりといった日本的な遊戯を講義の合間に取り入れたことがあった。
講義材料として日本から折り畳み式の将棋盤や駒、百人一首一揃いを持ち込んでいたので、どこかのタイミングで実施しようと考えていた。予定では生徒たちともっと打ち解けてからと思っていたが、日本クラスの参加者が早々に減少していったため、彼らの興味を少しでも繋ぎ留められたら、と急遽やってみることにしたのだ。
チューターであるマリーは自習室の受け持ちで、日本クラスは彼女の部屋を使用させてもらっていた。マリーは静寂を愛する人で、講義の最中に生徒がヒソヒソ話をしていたら「エ!」とか「オッオウ!」と注意を促していたし、ガヤガヤなどしようものなら
「静かにしないなら出て行って!」
と退出させる勢いだった。
そんな彼女のことをまだよく知らない初期段階での私は、
「今度の講義の時間に、日本のゲームをしてもいいですか?」
と忖度なしに尋ねてしまったのだ。マリーは分かりやすく眉をひそめ、
「騒がしいのはやめてね」
と口元をゆがめて言った。
最初に実施したのは坊主めくりだった。書道クラスを継続していた生徒に、和歌や俳句をしたためてもらうことにしていて、百人一首について講義で取り上げた直後だったということ、そしてこの遊戯であれば、マリーの意向にも配慮できると考えたからだった。
余談だが、坊主めくりには地方によって異なるルールがあるようで、私が幼い頃に教わったのは以下の通り。
①札をシャッフルしたあと、裏返して重ねる
②ジャンケンで勝った人から時計回りに、重ねた山から札を1枚引き、表に返して山の横に置く
③男性だった場合は、その札を自分の手元に持っておく
④女性だった場合は、その札を自分の手元に持っておき、更にもう1回引くことができる
⑤坊主(髪の毛がない男性)だった場合は、参加者全員がその札に手を付く
⑥手を付くのが一番遅かった人は、一番早かった人に自分の手札を全て渡す
⑦坊主ではない札に手を付いたときは、1回休み
⑧重ねた山がなくなったとき、一番多く手札を持っていた人が勝ち
聞いたところによると、私が教わったルールは、⑤⑥⑦が一般的な坊主めくりの遊び方とは違うらしい。そうとは知らなかったインターン当時の私は、自分の知っているルールが標準だと思っていたので、生徒たちには①~⑧を説明し、ゲームに臨んだのだった。
最初のうちはみんな男性か女性を引いていたので、ゲームは淡々と進行し、2巡くらいしたとき、誰かが坊主を引いた。一瞬、全員がビクッと身体を硬直させたのち、坊主札めがけて一斉に手を伸ばした。
バシン、という叩打音に続き、
「いって~!」
という叫び声が男子生徒から上がった。
「それ、反則だよ……。これ(坊主めくり)するときは、指輪を外して!」
どうやら、ごっつい指輪をした女子生徒が男子生徒の上から手を付いたようで、付かれた男子が文句を言ったのだ。
「ゴメンね。つい夢中になっちゃって」
女子生徒は笑って指輪を外し、凶器使うなよ~、すごく痛かった!と言って手をさする男子生徒を見て、他の生徒たちも談笑し始めたときだった。
「静かに!声を上げないで!」
マリーが険しい顔をして私たちに指摘した。
「すみません、マダム」
生徒たちは謝罪ののち首をすくめ、お互い目くばせし、ゲームを再開した。
しばらくは粛々と札が引かれていたが、坊主が引かれたらどうしたって手を付く音がするし、生徒たちも悲喜こもごもの反応をする。その都度マリーは不快そうな表情で私たちの様子を窺っていた。
日本クラスの時間が終了し、生徒たちが部屋を離れたあと、マリーから
「あのゲームはもうやらないで」
とダメ出しを受けた私は、別の機会に将棋崩しをやってみることにした。このゲームは崩さないようにとか音を立てないように集中するから、そうそう騒がしくなることはないだろう。私は坊主めくりの時と同じく事前にマリーに許可を求め、渋る彼女に
「今度のゲームは前みたいに騒がしくなったりしないから」
と説得した。
ちなみに、生徒たちに説明したルールは以下の通り。
①箱に入れた駒を将棋盤にひっくり返し、駒の山を作る
②ジャンケンで勝った人から時計回りに、駒の山から駒を指一本で抜き、抜いた駒を盤外へ出せたらその駒をもらえる
③駒を抜くとき音を立てたら次の人へ交代する
④駒を抜くとき山を崩してしまったら負け
⑤もらった駒の数が多い人が勝ち
実は、私が幼少期に父から教わった将棋崩しのルールは、抜いた駒を‟盤外に出す”のではなく、‟盤上で立てる(駒の接地面を変える)”という内容だった。立てるときも指一本でやらなくてはならないから、抜くときと立てるとき、2回集中する必要がある。私はこれが標準ルールだと思っていたのだけれど、小学生のとき同級生に
「お前のルールはおかしい」
と言われ、他の友達も立てるルールで遊んでいる人はいないようだったので、これはマイホームルールなのだと理解した。また、⑤は駒の種類によって点数を付けるパターンがあることも分かった。
日本クラスでの話に戻ると、坊主めくりより安全(?)だと思われた将棋崩しだったが、実際にはいきなりマリーのご不興を買った。彼女には、箱に入れた駒を将棋盤にひっくり返したときの音が耳障りだったようだ。
まだ、ゲーム始まる前なんですけど……。
雲行きが怪しいまま開始したところ、駒が音を立てたり山が崩れたりするたびに上がる生徒の抑えた悲鳴ですらマリーには耐えられなかったようだ。クラス終了後、将棋崩しには坊主めくりと同様に禁止令が出たのだった。
さすがに私も3回目のゲーム実施を許可してもらおうという気にはなれず、次に考えていた自作ゲームを封印することにした。
このゲームは私がニコと知り合ってから、日本語を始めたばかりの人が語彙力を増やすのにいいかな~とか、視力や聴力に障がいのある人とも一緒に遊べるかな~と思って考案したもので、『日光東照宮ゲーム』と名付けた。4人以上で対応可能。ルールは以下の通り。
①中が見えない箱もしくは布などで隠されているものを、見ザル(1番手)の人が触り、それを予想し、言わザル(2番手)に単語で伝える。具体的な答えとなるような単語はダメ。例えば、隠されているものがサッカーボールで、見ザルがサッカーボールだと予想した場合、丸い・20センチくらい・スポーツ用品などと伝えるのはOKだが、ボールとかサッカーボールと伝えるのはNG。
②言わザルは見ザルから伝えられた単語をもとに絵を描き、聞かザル(3番手)に伝える。
③聞かザルは言わザルの絵をヒントにして隠されているものを当てる。
④どうしても予想がつかない場合、見ザル・言わザル・聞かザルはそれぞれ1回だけ神様(出題者とか見ている人)に助けを求めることができる。その際、神道の作法(二拝二拍手一拝)をし、一芸を捧げてから聞きたいことを尋ねること。
⑤隠されたあるものを当てたら見ザル・言わザル・聞かザルの勝ち。
学校では実践しなかったけれど、ニコやホームステイしていたRDP家ではちょこっとやってみたことがある。長いこと忘れていたけれど、こんなゲームを考えたことがあったんだった。
最近、フランス語関連の集まりに参加させていただいていて、順番に発表の機会が巡ってきたりするので、そこでやってみようかしら?などと目論んでいる最中である。