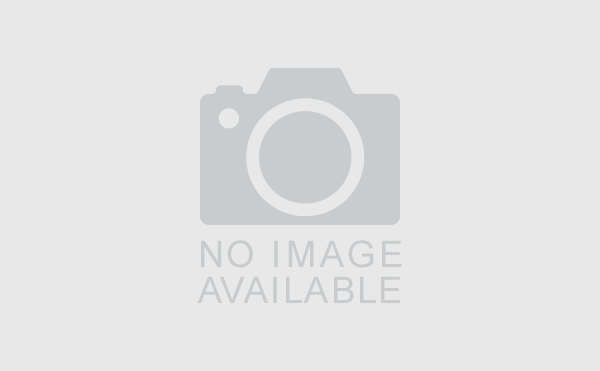25年振り、東京でも製本体験
かつてフランスに留学中、パリの工房で製本体験をした。
あの体験から25年の歳月を経て、このたび、新たに東京で製本に取り組む機会を得た。
今回は、文庫本を一度バラして上製本にするという体験。
一般的に、文庫本は接着剤や糸などで綴じられた並製本(ソフトカバー)が多く、表紙が中身の冊子と同じ大きさである。
一方、上製本(ハードカバー)は、硬い厚紙で冊子をくるんで製本するため、表紙が冊子より数ミリ大きい。
私がパリの工房で制作したのは上製本で、あのときは冊子にする紙を切断し、糸で綴じるところから始めた。当時、夢いっぱいで表紙デザインを考えたものの、自分のイメージしていた本にするためには、時間もお金も予想以上にかかることが判明。制作に取り掛かる前段階で、すでに落胆したり諦めたりしたことがあった(その話は、このサイト内『ある日、子牛の革と胡桃の樹』でご紹介しています)。
その後制作を開始してみて、確かにこれは期間も労力もコストも要するものだと理解した。先生である工房のマダムが、私の装丁デザインだと仕上げるのが難しいとおっしゃったときは、渋々受け入れたという感じだった。だが、帰国間際の短期間にいろいろ盛り込んだものを作ろうと思っていた私が浅はかだった。マダムの提案通りに制作したからこそ、何とか作り上げられたのだ。
今回は1日体験のワークショップ。かつて経験したときの記憶は、月日の流れとともに頭の中からも少しずつ流出した。私は1日で仕上げられるのか?!
25年前に制作した本を眺めて工程を思い返しながら、ワークショップに臨んだ。
今回は参加者が7人。制作時間は14:00~17:30。案内のメールには、‟3時間~3時間半かかる場合がある”と記載されていたので、参加者の皆さんが早々と完成しているなか、私一人だけ時間内に終わらなかったらどうしよう?!と、多少の不安を抱いた。
開始時間前に、持参した2枚の布のサイズを20×30cmにカットしてから、説明が始まった。
まず、講師の方がお手本で作る過程を拝見し、そのあとで参加者が作ってみるという流れ。制作工程を、参加者がついて行けそうな範囲で区切ってくださっているうえ、サポートの方々が適宜アドバイスをくださるので、誰かが置いて行かれたりすることなく、皆だいたい同じペースで作ることができていた。
それでも、制作時間を目いっぱい使用し、3時間半かけて完成!
最後に、参加者と講師や協会の方々が制作したもの、様々な色・柄の本を並べて写真を撮らせていただいた。
本当は、各工程の区切りで写真を撮るつもりだったのに、その余裕がなく……。
驚いたのは、参加者のお子さんがお絵描きした数枚の紙を、我々の完了と同じタイミングで、協会の方が製本されていたこと!
※写真手前左から2番目の黄緑の表紙が、協会の方制作・巨匠(お子さん)のお絵描き本

お母さんだけでなく、お子さんにも楽しい思い出になったことだろう。
協会の方の素敵なはからいに、このワークショップに参加できて良かった、と改めて感じた。
ワークショップは年に数回開催されているようなので、ご興味のある方はぜひ、協会のHPを一度ご覧になってみてください!
また、私がこのワークショップの参加を決めたのは、今回講師を務めてくださったのが、私がnoteでフォローしているやまねこさんだったから。
やまねこさんは新潟にお住まいで、ワークショップのために東京まで来られている。私がやまねこさんとお会いするのは、今回が初めて。
やまねこさんのnoteを拝見していると、毎日がアクティブかつバラエティに富んでいる。これだけ活動的だと、文章や写真から、引力とか迫り来る風とか、こちらも巻き込まれるような推進力を感じたりしそうなものなのに、いつもゆったり穏やかな気持ちにさせられる。私が、アクティブ=せかせか、という印象を持ちがちだったからなのかも知れないけれど、やまねこさんの文章や写真からは、遊牧民とかキャラバンのような、悠然とした雰囲気を感じる。遊牧民やキャラバンに出逢ったことはないので、いい加減なイメージで済みません……。
やまねこさんがアップしている内容が気になる方は、ぜひ、noteでご確認ください!